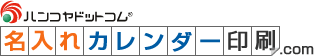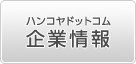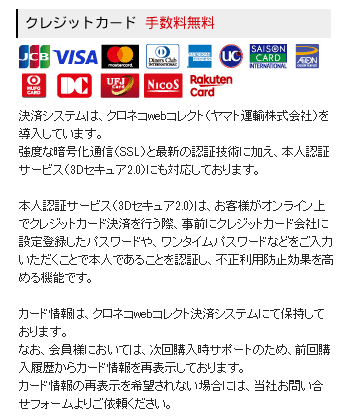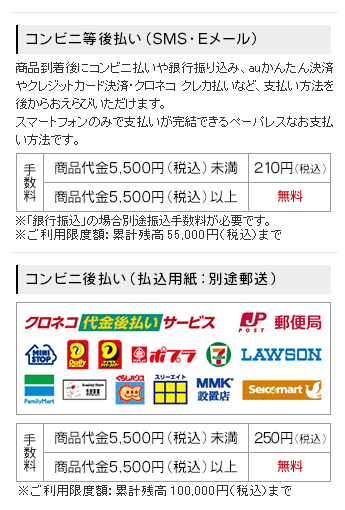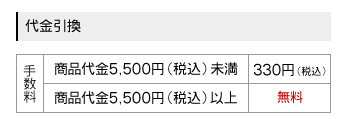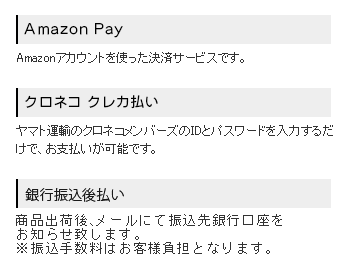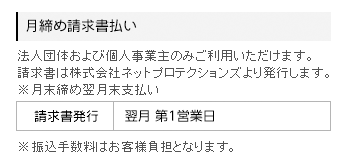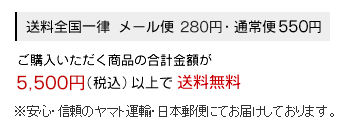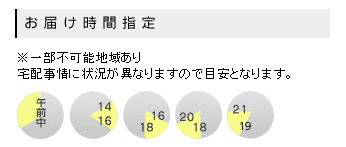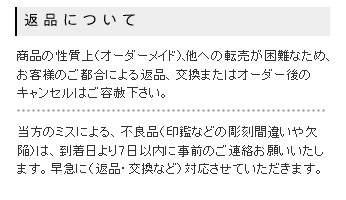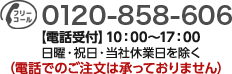土用の丑の日とは
土用の丑の日(どようのうしのひ)とは、立春・立夏・立秋・立冬の前の約18日間(土用)にある「丑の日(うしのひ)」のことです。
「土用」とは季節の変わり目を示す期間であり、「丑の日」とは日にちを十二支で数えた際に丑にあたる日です。
- 土用:季節の変わり目の約18日間
- 丑の日:十二支で「丑(うし)」にあたる日
- 土用の丑の日:土用の期間中にある丑の日
つまり、簡単にいえば、土用の丑の日は「季節の変わり目に訪れる丑の日」を指します。
そのため、土用の丑の日は年に複数回ありますが、一般的には夏の土用にある丑の日を指すことがほとんどです。
土用は季節の変わり目で体調を崩しやすいため、昔から食べ物で体調を整える「土用の食養生」という考え方がありました。
とくに夏の土用の丑の日には、「う」のつく食べ物を食べると夏バテしないとされ、うなぎを食べる習慣が有名です。

- 十二支とは
-
十二支(じゅうにし)とは、「子(ね)・丑(うし)・寅(とら)・卯(う)・辰(たつ)・巳(み)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)」の12種類の動物です。
辰年(たつどし)、午年(うまどし)のように年を表すときに使われますが、時刻や方角、日を示す場合にも用いられます。
一の丑・二の丑とは
丑の日は12日周期のため、約18日間の土用の期間内に丑の日が2回巡ってくる年があります。
同じ季節の土用の期間中に丑の日が2回ある場合、1つ目を「一の丑(いちのうし)」、2つ目を「二の丑(にのうし)」と呼びます。
丑の日が2回訪れることは縁起が良いとされ、一の丑は「夏本番前のスタミナ補給日」、二の丑は「暑さのピークに再び体力をつける日」とされています。
スーパーなどのうなぎ売り場では、販促のために一の丑・二の丑で売り方に変化をつけるところもあるようです。
土用の丑の日はいつ?2026年・2027年のカレンダー
2026年・2027年の土用の丑の日をまとめました。
立春・立夏・立秋・立冬の日付は毎年変動するため、それに応じて土用の丑の日の日程・日数も変わります。
【2026年】土用の丑の日
- 1月27日(火)
- 4月21日(火)
- 5月3日(日)
- 7月26日(日)
- 10月30日(金)
【2027年】土用の丑の日
- 1月22日(金)
- 2月3日(水)
- 4月28日(水)
- 7月21日(水)※一の丑(いちのうし)
- 8月2日(月)※二の丑(にのうし)
- 10月25日(月)
- 11月6日(土)
土用の丑の日にうなぎを食べる理由・由来
土用の丑の日にうなぎを食べる理由には、大きく2つあります。
丑の日」に「う」がつく食べ物が良いとされた
土用は季節の変わり目で体調を崩しやすい時期とされ、古くから食べ物で体を労わる習慣がありました。
春の土用は「戌(いぬ)」、夏の土用は「丑(うし)」、秋の土用は「辰(たつ)」、冬の土用は「未(ひつじ)」の日に、それぞれの頭文字がつく食べ物を食べると良いとされました。
夏に食される「う」のつく食べ物には、うどん、梅干し、瓜(うり)、うなぎ、馬肉、牛肉などがあり、体力回復や夏バテ防止に役立つとされています。
実際、日本最古の歌集『万葉集』にも「夏痩せにはうなぎがよい」と詠まれており、少なくとも奈良時代にはうなぎの滋養効果が認識されていたようです。
- 春・秋・冬の土用に、健康に良いとされる食べ物
-
夏の土用に比べて知名度は低いですが、他の季節では以下の食材が健康に良いとされています。
- 【春の土用】「戌(いぬ)」の日に「い」のつく食べ物
(例)いちご、イカ、いわし、いなり寿司、インゲン豆、芋など - 【秋の土用】「辰(たつ)」の日に「た」のつく食べ物
(例)タコ、玉ねぎ、大根など - 【冬の土用】「未(ひつじ)」の日に「ひ」のつく食べ物
(例)ひじき、ヒラメ、ヒラマサなど
- 【春の土用】「戌(いぬ)」の日に「い」のつく食べ物
栄養豊富なうなぎは、夏の疲労回復におすすめ
うなぎは、ビタミンA、B群や鉄分、カルシウムなど栄養素が豊富で、夏場の疲労回復・食欲不振をケアするのにピッタリです。
とくにビタミンAは、皮膚や粘膜を正常に保つことでウイルス・病原菌の侵入を防ぎ、免疫力アップに効果があります。
なお、うなぎ100gを食べれば、男性の一日におけるビタミンAの必要摂取量をまかなえます。
また、うなぎは良質なたんぱく質源でもあるため、暑さで消耗した体にエネルギーを補給する食材としても最適です。
- 現代では、うなぎを食べる必要がない?
-
江戸時代に比べて、現代は栄養価の高い食材が増えたため、ビタミン・エネルギー不足で夏バテになる可能性は低いとされています。
そのため、「現代の日本において、夏バテ防止のためにうなぎを食べる必要性は薄い」とする考えもあります。また、近年ではニホンウナギの漁獲量が減少していることから、絶滅を危惧して土用の丑の日にうなぎを販売しない店もあるようです。
うなぎ屋を救うために、平賀源内が宣伝した
奈良時代からうなぎが夏バテに効くことは知られていましたが、土用の丑の日にうなぎを食べる風習が始まったのは江戸時代です。
江戸時代に主流だった天然うなぎは秋・冬が旬のため、夏にはうなぎが売れませんでした。
そこで困ったうなぎ屋が、蘭学者・発明家の平賀源内(ひらがげんない)に相談を持ちかけたところ、「本日丑の日」という張り紙を店先に貼るよう勧められます。
もともと丑の日に「う」のつく食べ物を食べる風習があったことから、張り紙によってうなぎ屋は繁盛し、土用の丑の日にうなぎを食べる習慣が広まったといわれています。
- うなぎを食べる習慣の由来には諸説あります。
うなぎ以外の土用の丑の日の食べ物
うどん
うどんはのどごしが良く、食欲が落ちる時期にも取り入れやすいメニューです。
同じく「う」のつく食材である梅干しと合わせると、程よい酸味で食も進みます。
冷やしうどんにするとツルッと食べられますし、ミョウガ・シソなどの薬味や野菜を添えると、栄養バランスも意識できますよ。
瓜(うり)
きゅうり、ゴーヤ、ズッキーニ、スイカといった夏に旬を迎えるウリ科の野菜は、ビタミンやミネラルが豊富です。
とくにウリ科の注目成分であるカリウムは、体内の余分な塩分を排出する作用があり、高血圧の予防にも効果があります。
また、きゅうり・スイカは水分を多く含んでいるため、夏の暑い時期の水分補給にも一役買っています。
なお、現代では瓜を食べる機会が減りましたが、うなぎの箸休めに出される奈良漬として残っています。
梅干し
梅干しには、疲労回復に効果があるクエン酸が多く含まれ、塩分補給にも役立ちます。
暑い時期は汗とともにミネラルを失いやすいため、夏バテ対策として古くから重宝されてきました。
おにぎりの具やおかずとして手軽に取り入れられるのも魅力です。
ちなみに、梅干しは6月頃に収穫した梅を塩漬けにし、梅雨明け後の土用の期間に「土用干し」、最後に本漬けをすると完成します。
また、梅干しは健康に良く「難が去る」といわれることから、ナン(難)がサル(去る)の語呂合わせで7月30日が梅干しの日に制定されています。
土用餅
土用餅(どようもち)とは、土用の時期に食べるあんころ餅(あんこ餅)のことです。
厄除けに効果があるとされる小豆あんと、力がつくとされる餅の組み合わせから、食べると無病息災で過ごせると考えられています。
夏の疲れた体に嬉しい甘味として、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょう。
なお、北陸地方には、小豆あんの代わりに塩味のササゲの豆(煮豆)をまぶした「ささげ餅」を食べる風習があります。
土用しじみ
しじみには肝臓の働きを助けるオルニチンが含まれており、夏バテを和らげる効果が期待できます。
夏の土用シーズンにしじみを食べる習慣は、うなぎの習慣より以前からあったといわれています。
しじみは夏と冬に旬があり、産卵前で身がぷりぷりと太った夏のものは「土用しじみ」と呼ばれます。
とくに宍道湖のしじみが有名で、味噌汁に入れたり、酒蒸しなどでうま味を引き出すのがおすすめです。
土用たまご
卵の旬が夏というわけではありませんが、江戸時代から、滋養をつけるために夏の土用に卵を食べる風習がありました。
現代ではいつでも新鮮な卵が手に入りますが、当時は卵が贅沢品だったため、夏バテ対策には最適の食材だったようです。
卵には、ビタミンCと食物繊維以外のすべての栄養成分が含まれるため、完全栄養食品ともいわれています。
調理方法としても、シンプルにゆで卵や卵焼き、丼ものの具材などアレンジしやすい点も魅力です。
土用の丑の日の風習・行事
きゅうり加持(かじ)
きゅうり加持とは、人間の肉体に見立てたきゅうりに、夏の疫病や災いを封じ込める土用の丑の日の風習です。
弘法大師・空海が広めた真言密教の秘法とされ、日本各地の寺院で行われています。
病気平癒・健康増進を祈願し、祈祷を終えたきゅうりは土の中に埋められます。
- きゅうり加持は、きゅうり加持祈祷会・きゅうり封じとも呼ばれます。
丑湯(うしゆ)
丑湯とは、無病息災を願って、土用の丑の日に薬草などを入れたお風呂に入る習慣のことです。
ももの葉・よもぎなどを入れた江戸時代の方法にならい、一部の銭湯ではそれを再現した「ももの葉湯」が実施されています。
丑湯は、暑い時期にこそ湯につかって疲れを癒そうとする先人の知恵といえるでしょう。
土用干し(どようぼし)
夏の土用の期間は梅雨明けのため、晴天が続きます。
そのシーズンに、さまざまなものを天日干しする習慣を「土用干し」といいます。
3つの土用干しの内容を表にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
| 概要 | 意味 | 別名 |
|---|---|---|
| 塩漬けした梅の実を、天日干しすること |
|
なし |
| 衣類や靴、本を陰干しすること |
|
|
| 田んぼの水を抜き、土にヒビが入るまで乾燥させること |
|
|
土用の期間にしてはいけないこと
土用の丑の日を含め、土用の期間に避けた方がよいことは、以下の3つです。
土を動かすこと
土用の期間は、土公神(どくしん・どこうしん)という土を司る神が支配するとされるため、土を動かす行為は避けるべきといわれます。
具体的には、以下のようなものです。
- 土いじり
- 草刈り・草むしり
- 柱立て
- 基礎工事・増改築
- 壁塗り
- 井戸掘り
- 地鎮祭 など
ただし、土用の前から着手していた作業は問題ないとされます。
- 約18日間ある土用のうち、「間日(まび)」と呼ばれる日には土を動かしてもよいとされます。
就職・結婚などの新しいこと
土用の期間は、就職・結婚などの新しいことは避けた方がよいとされています。
具体的には、以下のようなものです。
- 就職・転職
- 結婚・結納
- 開業・開店
- 新居購入 など
このシーズンは季節の変わり目で体調を崩しやすいため、静かに過ごした方がよいという考えが生まれたようです。
ただし、土用であることを意識しすぎると、人生の節目に最適なタイミングを逃す可能性もあるため、総合的に判断するのがよいでしょう。
旅行・引っ越しなどの移動
土用の期間に、旅行・引っ越しなど場所を変える行動は避けた方がよいとされます。
これは、土用の期間はすべての方位(方角)が良くないと考えられているためです。
また、「土用殺(どようさつ)」という土用の期間に凶とされる方位もあり、この方角には特に注意が必要です。
「土用殺」は、季節によって変わるため、事前にチェックしておきましょう。
| 土用の季節 | 方角(土用殺) |
|---|---|
| 春の土用 | 南東 |
| 夏の土用 | 南西 |
| 秋の土用 | 北西 |
| 冬の土用 | 北東 |
まとめ
土用の丑の日は、季節の変わり目である土用と、十二支の丑の日が重なる日です。
特に夏の土用の丑の日には、夏バテを予防するために「う」のつく食べ物が食べられています。
各地で健康・厄除けの行事も行われるなど、日本ならではの伝統文化に触れるよい機会でもあります。
土用の丑の日の由来・意味を知り、季節の変化に寄り添った暮らしの知恵として活かしてみてはいかがでしょう。