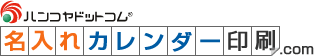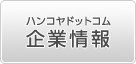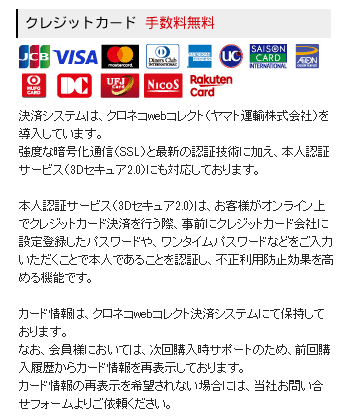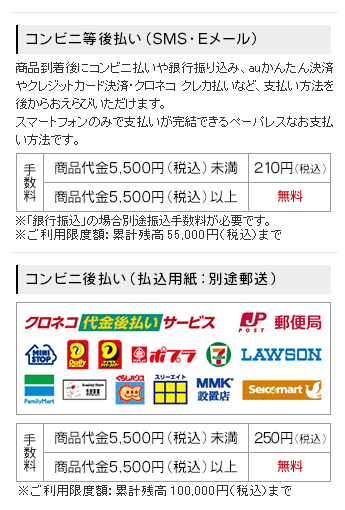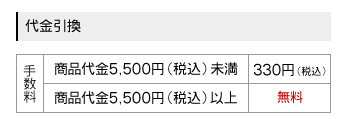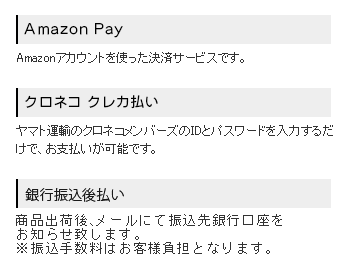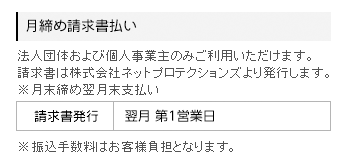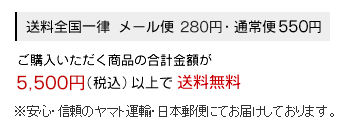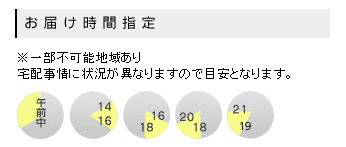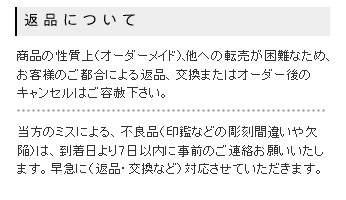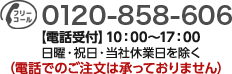和風月名とは「旧暦における12ヶ月の名前」
和風月名(わふうげつめい)とは、明治5年まで旧暦(太陰太陽暦)で使われた月の名前のことで、1月の「睦月(むつき)」・2月の「如月(きさらぎ)」などの和風の呼び方を指します。
和風月名の呼び名は、旧暦の季節・行事を反映した風情のある響きとなっており、現代の季節とは1〜2ヶ月ほどずれています。
なお、和風月名の語源には諸説あるため、はっきりしたことはわかっていません。
とはいえ、奈良時代(720年)に成立した日本最古の歴史書である「日本書紀」には、月の数字表記のそばに和風月名がカタカナの訓読みとして書かれているため、起源は古いようです。
「日本書紀」に見られる和風月名の表記例
- 二月(キサラギ)
- 十有一月(シモツキ)
- 十有二月(シハス)
現代では新暦(グレゴリオ暦)が主流となり、日常生活で和風月名を使うことは少なくなりましたが、歳時記や手紙の時候の挨拶、文学作品などで今も用いられています。
日本の伝統や四季を表現する言葉として、和風月名は今も大切に受け継がれています。

- 旧暦とは
-
旧暦とは、月の満ち欠けで1か月を定める「太陽太陰暦」のことで、一般的には天保15年(1844年)から明治5年(1872年)まで使用された「天保暦」を指します。
月の満ち欠けの周期は約29.5日のため、旧暦における1年間の日数は約29.5日×12ヶ月=約354日となり、現在使われている新暦より約11日短くなっています。一方で、現代において使用される新暦(グレゴリオ暦)は、太陽の動きがベースのため「太陽暦」と呼ばれます。
旧暦と新暦の違いは、「旧暦は月の動き・新暦は太陽の動きを基準にしている」と覚えるとよいでしょう。
和風月名の一覧と由来
ここからは、1月から12月までの和風月名の由来(語源)、読み方をご紹介します。
和風月名の由来には諸説ありますが、ここでは代表的なものをベースに解説していきます。
それぞれの月の異称(別の呼び名)もまとめているので、季節感を掴むためにもぜひ参考にしてください。
1月:睦月(むつき)
旧暦の1月は「睦月(むつき)」と呼ばれ、現在の暦で1月下旬〜3月上旬頃を指します。
正月に親族や友人が集まり、仲睦まじく過ごすことから「睦月」と呼ばれるようになったとされます。
その他には、稲の実を初めて水に浸す「実月(むつき)」や「生月(うむつき)」が転じた説もあります。
- 睦月以外の1月の異称(一例)
-
- 初春月(はつはるづき):春の始まり
- 太郎月(たろうづき):最初の月
- 早緑月(さみどりづき):木々の緑が芽吹き始める頃
- 健寅月(けんいんげつ):十二支の寅にあたる月
2月:如月(きさらぎ)
旧暦の2月は「如月(きさらぎ)」で、現在の暦で2月下旬から3月上旬頃を指します。
まだ寒さが残る時期で、「冷えから体を守るため重ね着をする(更に着る)月」という意味の「衣更着(きさらぎ)」が有力な語源です。
他には、春に向けて草木が生え始める「生更木(きさらぎ)」、天気が良くなり陽気が増す「気更来(きさらぎ)」などが由来とされています。
なお、「如月」の表記は、中国最古の辞書『爾雅(じが)』にある「二月を如となす」という記述にルーツがあります。
ただし、「如月」を「きさらぎ」と読むのは日本だけで、中国では「にょげつ」「じょげつ」と読みます。
- 如月以外の2月の異称(一例)
-
- 仲春(ちゅうしゅん):春3ヶ月の真ん中の月
- 恵風(けいふう):春風が吹く頃
- 雪解月(ゆきげづき):雪が解け始める月
- 令月(れいげつ):何をするのにも良い月 (元号「令和」の由来)
3月:弥生(やよい)
3月の旧暦名称は「弥生(やよい)」で、現在の暦で3月下旬〜5月上旬頃を指します。
暖かくなる季節に草木がさらに生い茂る「木草(きくさ)弥(いや)生(お)ひ茂る月」という表現が語源とされています。
- 弥生以外の3月の異称(一例)
-
- 辰月(しんげつ):十二支を12か月に当てはめたもの
- 禊月(けいげつ):古代中国で3月3日に禊(みそぎ)を行っていたことに由来
- 花見月(はなみづき):桜などの春の花が咲き誇る月
- 桜月(さくらづき):桜が本格的に開花する月
4月:卯月(うづき)
旧暦の4月は「卯月(うづき)」で、現在の暦で4月下旬〜6月上旬頃を指します。
卯月の由来には「卯(うずき)の花が盛りになる月」、田植えの「植え月」などがあります。
旧暦においては、卯月から夏が始まるため、衣替えはこの頃に行われていたといわれています。
- 卯月以外の4月の異称(一例)
-
- 卯の花月(うのはなづき):卯の花が咲く月
- 夏初月(なつはづき):夏の初めの月
- 麦秋(ばくしゅう):麦の収穫時期で、麦にとっての秋を指す
- 清和(せいわ):空が澄み清らかな時期
5月:皐月(さつき)
5月の和風月名は「皐月(さつき)」で、現在の暦で5月下旬から7月上旬頃を指します。
皐月は田植えを意味する「早苗月(さなえづき)」が略されて生まれた名前で、「皐」の漢字は水田・水ぎわを表します。
また、「皐月(さつき)」の「さ」には田の神様、または田の神様に捧げる稲という意味もあります。
- サツキの花は、皐月の頃に咲くことから名づけられたもので、皐月の語源ではありません。
- 皐月以外の5月の異称(一例)
-
- 仲夏(ちゅうか):夏3ヶ月の真ん中の月
- 菖蒲月(あやめづき):菖蒲の花が咲く月
- 五月雨月(さみだれづき):梅雨の月
- 田草月(たぐさつき):稲に交じって雑草が生える月
6月:水無月(みなづき、みなつき)
6月の旧暦名称は「水無月(みなづき、みなつき)」で、現在の暦で6月下旬〜8月上旬頃を指します。
よく勘違いされますが、水無月の「無」は連体助詞「の」の意味で、「ない」の意味ではありません。
水無月の頃に田んぼに水を張ることから「水の月」となり、「水無月」という和風月名が生まれたとされています。
上記以外の由来には、田植えという大仕事をみんなでやり尽くした「皆仕尽(みなしつき)」や「暑さで水が干上がる水のない月」という説があります。
- 水無月以外の6月の異称(一例)
-
- 風待月(かぜまちづき):暑さで風が吹くのが待ち遠しい月
- 鳴神月(なるかみづき):雷が多い月
- 青水無月(あおみなづき):青葉が茂る水の月
- 葵月(あおいづき):葵の花が咲く月
7月:文月(ふみづき、ふづき)
旧暦の7月は「文月(ふみづき、ふづき)」で、現在の暦で7月下旬〜9月上旬頃を指します。
文月の由来は、七夕の夜に書物を開いて夜気にさらし、字の上達を願う風習「文披月(ふみひらきづき・ふみひろげづき)」とされています。
また、稲穂が膨らむ時期を指す「穂含月(ほふみづき)」や「含月(ふふみづき)」が、文月に転じた説もあります。
- 文月以外の7月の異称(一例)
-
- 七夕月(たなばたづき):七夕のある月
- 秋初月(あきはづき):秋の初めの月
- 親月(おやづき、しんげつ):盂蘭盆会(お盆)の時期で、親の墓参りに行く月
- 女郎花月(おみなえしづき):秋の七草である女郎花の花が咲く月
8月:葉月(はづき、はつき)
8月の和風月名は「葉月(はづき、はつき)」で、現在の暦で8月下旬から10月上旬頃を指します。
秋に葉が落ちる「葉落月(はおちづき)」が有力な語源ですが、稲の穂が張る「穂張月(ほはりづき)」・雁(がん)が渡ってくる「初雁月(はつかりづき)」が由来の説もあります。
- 葉月以外の8月の異称(一例)
-
- 月見月(つきみづき):中秋の名月(旧暦8月15日の月)を鑑賞する月
- 燕去月(つばめさりづき):燕(つばめ)が南に渡る月
- 木染月(こぞめづき):紅葉が始まる月
- 竹春(ちくしゅん):タケノコが若葉を茂らせ成長する様子
9月:長月(ながつき、ながづき)
旧暦の9月は「長月(ながつき、ながづき)」で、現在の暦で9月下旬〜11月上旬頃を指します。
秋の夜長を意味する「夜長月(よながづき)」が有力な語源とされますが、秋の長雨の「長雨月(ながめづき)」・稲穂が実る「穂長月(ほながづき)」が転じた説もあります。
- 長月以外の9月の異称(一例)
-
- 紅葉月(もみじづき):紅葉の時期
- 菊月(きくづき):菊の花が咲く月
- 詠月(えいげつ):月を眺めながら和歌を詠む月
- 寝覚月(ねざめづき):夜が長く、暗いうちに目覚めやすい月
10月:神無月(かんなづき)
10月の和風月名は「神無月(かんなづき)」で、現在の暦で10月下旬から12月上旬頃を指します。
6月の水無月と同じく、神無月の「無」は連体助詞「の」の意味で、「ない」の意味ではありません。
旧暦10月には農作物の実りを神に感謝する収穫祭が行われていたため、「神の月」から「神無月」という名称ができました。
また、神無月には全国の神様が出雲大社へ集まるため、他の地域から神様がいなくなる(神が無い)ことも由来とされています。
そのため、島根県の出雲地方では、旧暦10月を神無月ではなく「神在月(かみありづき)」と呼んでいます。
- 神無月以外の10月の異称(一例)
-
- 雷無月(かみなしづき、かみなかりづき):雷が鳴らなくなる頃
- 神嘗月(かんなめづき):伊勢神宮で神嘗祭(かんなめさい)が行われる月
- 小春(こはる):小春日和の月
- 初霜月(はつしもづき):初霜が降りる頃
11月:霜月(しもつき)
11月の旧暦名称は「霜月(しもつき)」で、現在の暦で11月下旬〜1月上旬頃を指します。
霜月の名前は、文字通り「霜が降りる時期」に由来しています。
- 霜月以外の11月の異称(一例)
-
- 神帰月(かみきづき):神無月で留守にしていた神様が各地に帰る月
- 神楽月(かぐらづき):神楽が盛んに行われる月
- 雪待月(ゆきまちづき):雪が降る月
- 食物月(おしものづき):新嘗祭(にいなめさい)で、食物(おしもの)に感謝する月
12月:師走(しわす)
旧暦の12月は「師走(しわす)」で、現在の暦(新暦)で12月下旬~2月上旬頃を指しますが、同時に新暦の12月の別名としても用いられています。
12月は僧侶(師)にお経を読んでもらったり、神社や寺を参拝する人が増える月のため「師と呼ばれる人々が、年の終わりに忙しく走り回る月」=「師走」となりました。
その他、年が終わるという意味の「歳終(としはつ)」「年果つ(としはつ)」、四季が果てる「四極(しはつ)」などが師走に転じた説もあります。
- 師走以外の12月の異称(一例)
-
- 限月(かぎりのつき、かぎりづき):節目の月
- 暮歳(ぼさい):年の暮れのこと
- 春待月(はるまちづき):新春を期待し、春を心待ちにする月
- 極月(ごくげつ):1年が極まる最後の月
和風月名の覚え方
旧暦の月である和風月名を丸暗記するのは大変ですが、「それぞれの月が当時の人々にとってどんな月だったか?」をイメージと覚えやすくなります。
また、月の数字を和風月名の意味と関連付ければ、さらに印象に残ります。
独自の語呂合わせも含め、和風月名の覚え方を下記表にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
| 月 | 和風月名 | 覚え方 |
|---|---|---|
| 1月 | 睦月 (むつき) |
|
| 2月 | 如月 (きさらぎ) |
|
| 3月 | 弥生 (やよい) |
|
| 4月 | 卯月 (うづき) |
|
| 5月 | 皐月 (さつき) |
|
| 6月 | 水無月 (みなづき、みなつき) |
|
| 7月 | 文月 (ふみづき、ふづき) |
|
| 8月 | 葉月 (はづき、はつき) |
|
| 9月 | 長月 (ながつき、ながづき) |
|
| 10月 | 神無月 (かんなづき) |
|
| 11月 | 霜月 (しもつき) |
|
| 12月 | 師走 (しわす) |
|
和風月名を覚えるには、和歌や短歌、俳句などの文学に触れてみるのも効果的です。
文芸作品の中でどのように和風月名が使われているかを知ると、単なる言葉以上に、当時の人々がその月に寄せた思いや季節の情景が見えてきます。
暗記するだけでなく、背景となる文化や歴史を感じながら学ぶことで、和風月名をより深く、豊かに味わえるようになるでしょう。
現代の暮らしで、和風月名を楽しむアイデア
古風な響きを持つ和風月名は、日常に取り入れることでぐっと身近に感じられるようになります。
ここでは、ビジネスや家庭で和風月名を活用し、日本的な風情を楽しむ方法をご紹介します。
ビジネスメールや年賀状に添える
形式ばった挨拶の中に和風月名を加えると、文章全体に季節の彩りや風情が生まれます。
- 例えば…
-
- ビジネスメールの冒頭に「文月も半ばを過ぎ、夏の暑さが本格化してまいりましたね」と添える
- 年賀状に「睦月の折、皆さまのご健康とご多幸をお祈りいたします」と書く
とはいえ、無理に難しい表現をする必要はなく、「霜月ですね」と一言添えるだけでも十分に相手に伝わります。
子どもの名前のアイデアにする
「弥生」「葉月」など、和風月名は上品な名前のアイデアとして人気があります。
「文」のように一文字を取るだけでも季節感のある響きになるので、子どもの名付けに困ったときは参考にするとよいでしょう。
子どもの誕生月の和風月名を使うと、季節の豊かさを名前の個性にできるのもメリットです。
インテリア・食卓のテーマにする
和風月名を季節のインテリアや食卓に軽く取り入れると、普段の暮らしが特別になります。
- 例えば…
-
- 6月(水無月):ガラスの器や青い花で、水や涼を演出
- 11月(霜月):白い小花や温かみのある陶器で、冬の訪れを表現
ちなみに、国立国会図書館が運営する「NDLイメージバンク」では、和風月名に対応する錦絵を閲覧できます。
江戸時代の暮らし・文化を和風月名ごとにチェックできるので、当時の風土から暮らしのヒントを得たい方におすすめです。
まとめ
和風月名は、旧暦に基づく12か月の呼び名で、それぞれの月の季節や行事、自然の移ろいを反映した風情ある名称です。
現代では日常生活で使う機会は少なくなりましたが、歳時記や文学、年賀状、ビジネス文書などで今も用いられています。
和風月名の覚え方のコツは、各月の意味や当時の人々の暮らしを想像し、単なる暗記にしないことです。
メールや季節のインテリアに取り入れれば、日常に日本的な風情を演出できるでしょう。