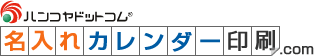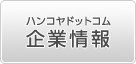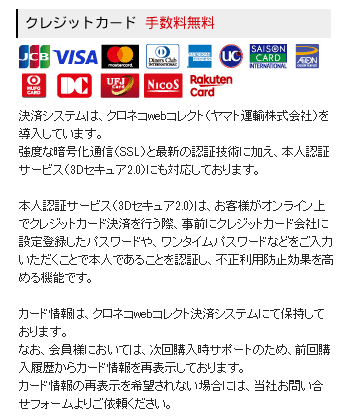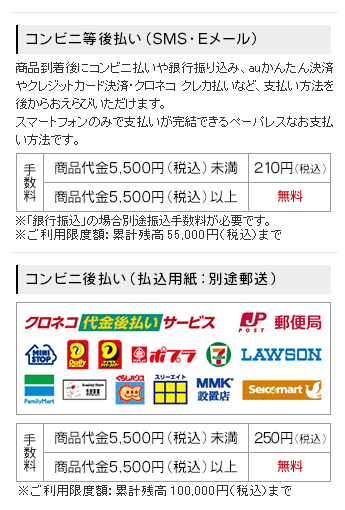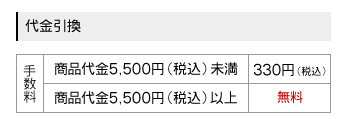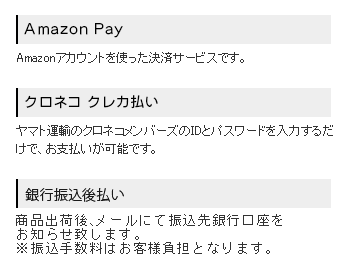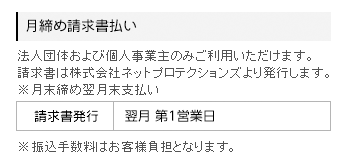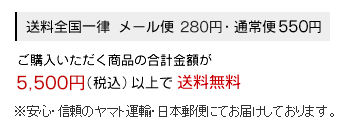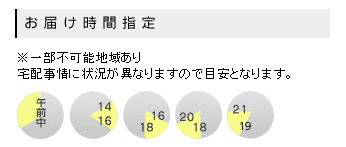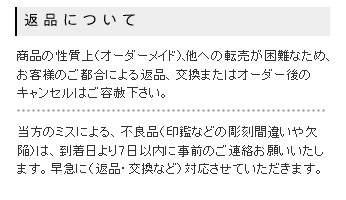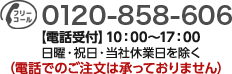【早見表でわかる】祝日と祭日の違い
祝日と祭日の違いは、「法律で定められた日かどうか」です。
祝日は現行法に基づく「国民の休日」ですが、祭日は戦前に存在した制度に基づく「宗教的・皇室的行事の日」で、今の法律上には存在しません。
そのため、現在の日本において法律上の休日は「祝日」のみです。
表にまとめると、以下のようになります。

| 祝日 | 祭日 | |
|---|---|---|
| 定義 | 「国民の祝日に関する法律」で定められた休日 | かつて「皇室祭祀令」で定められた、宗教的な儀礼を行う日 |
| 根拠となる法律 | 国民の祝日に関する法律 | 皇室祭祀令(1947年に廃止) |
| 現在の扱い | 国民の休日として存在 | 今の法律上には存在しない ※一部は祝日に引き継がれた |
| 例 | 成人の日、建国記念の日など | 紀元節、新嘗祭など |
祝日とは
祝日とは、「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」)」によって定められた、国が制定する休日のことです。
祝日の正式名称は「国民の祝日」で「元日」や「成人の日、」など年間で16日が設定されています。
また、祝日は単なる休みではなく、「国民全体で日本の文化や伝統を受け継ぎ、よりよい社会を築く」ことが目的とされています。
祝日には、以下の3種類があります。
| 国民の祝日 | 国によって定められた、仕事や学校が休みになる日 |
|---|---|
| 振替休日 | 日曜日が祝日と重なった場合に、代わりに休みになる日 |
| 国民の休日 | 祝日ではないが、祝日と祝日に挟まれた平日で休みになる日 |
このうち「振替休日」と「国民の休日」は、法律上は「国民の祝日」とは別の扱いです。
ただし、実際には祝日と同様に休みになるため、一般的には祝日の一種としてまとめて紹介されることが多くなっています。
振替休日・国民の休日は、特定の祝日が日曜日になった場合でも、国民が休みを取りやすくするための制度です。
とくに国民の休日は、祝日同士に挟まれた平日を休日とし、連休を作り出す制度のため、観光・レジャー業界に恩恵をもたらしています。
祝日には、日付が固定のもの・変動するものがある
祝日には、「日付が毎年固定されているもの」と「年によって日付が変わるもの」があります。
たとえば、1月1日の「元日」や2月11日の「建国記念の日」、11月3日の「文化の日」などは毎年同じ日付の祝日です。
一方で、「成人の日」「海の日」「敬老の日」「スポーツの日」は「○月の第△月曜日」と定められており、年によって日付が変わる祝日です。
これら月曜日に固定されている祝日は、3連休をつくりやすくする「ハッピーマンデー制度」によって定められています。
- ハッピーマンデー制度とは
-
ハッピーマンデー制度は、祝日を特定の月曜日に移動させることで、連休を増やす仕組みです。
国民が休暇を取りやすくすることを目的に、1998年に法改正され、2000年から実施されました。
現在は「成人の日」「海の日」「敬老の日」「スポーツの日」がこの制度の対象となっています。
また、「春分の日」と「秋分の日」は、天文学的な計算によって毎年日付が変わる特殊な祝日です。
これらは法律で具体的な日付が定められておらず、国立天文台が太陽の位置などから算出し、翌年分を毎年2月に発表する「暦要項(れきようこう)」に記載されて正式に確定します。
そのため、春分の日は3月20日頃、秋分の日は9月22日頃になりますが、年によって1日前後します。
祭日とは
祭日は、皇室の祭典や神社のお祭りに関わる宗教儀礼の日を指し、かつては「皇室祭祀令(こうしつさいしれい)」という法律で定められていました。
当時、一部の祭日は休日でしたが、戦後の法整備により祝日法が整備された結果、現在では祭日は廃止されています。
そのため、祭日はカレンダーにも公式には記載されていません。
過去にあった祭日の例としては、紀元節(きげんせつ)や新嘗祭(にいなめさい)などがあります。
- 今も名残がある「祭日」
-
現在も「新嘗祭(にいなめさい)」や「神嘗祭(かんなめさい)」などの皇室行事は続いており、宮中では伝統的な祭祀として行われています。
ただし、これらは国民の祝日ではなく、皇室の行事日として扱われています。
祝日に引き継がれた祭日・廃止になった祭日の一覧
1947年に皇室祭祀令が廃止されたタイミングで、祭日は①祝日に引き継がれたもの②廃止になったものの2パターンに分かれました。
祝日に引き継がれた祭日
| 過去に存在した祭日 | 現在の祝日 | 日付 |
|---|---|---|
| 四方節(しほうせつ) | 元日 | 1月1日 |
| 紀元節(きげんせつ) | 建国記念の日 | 2月11日 |
| 春季皇霊祭(しゅんきこうれいさい) | 春分の日 | 3月20日頃(毎年変動) |
| 昭和天皇の誕生日 | 昭和の日 | 4月29日 |
| 秋季皇霊祭(しゅうきこうれいさい) | 秋分の日 | 9月22日頃(毎年変動) |
| 明治節(めいじせつ) | 文化の日 | 11月3日 |
| 新嘗祭(にいなめさい) | 勤労感謝の日 | 11月23日 |
- 昭和の日は、平成元年~平成18年までは「みどりの日」とされていました。現在「みどりの日」は5月4日へ移動しています。
廃止になった祭日
| 過去に存在した祭日 | 当時の日付 |
|---|---|
| 元始祭(げんしさい) | 1月3日 |
| 新年宴会(しんねんえんかい) | 1月5日 |
| 神武天皇祭(じんむてんのうさい) | 4月3日 |
| 神嘗祭(かんなめさい) | 10月17日 |
| 大正天皇祭(たいしょうてんのうさい) | 12月25日 |
【2026年版】祝日の一覧・意味
2026年の「国民の祝日」をまとめました。
それぞれ独自の意味があるので、背景を知っておくと休みの日をより有意義に過ごせるでしょう。
なお、下記表に振替休日は含まれていません。
| 祝日の名称 | 日付 | 意味・由来 |
|---|---|---|
| 元日 | 1月1日 | 一年のはじまりを祝い、新しい年の平安を願う日 |
| 成人の日 | 1月12日 | 大人になった自覚を持ち、自分の力で生き抜こうとする若者を祝い励ます日 |
| 建国記念の日 | 2月11日 | 日本の建国をしのび、国を愛する心を育む日 |
| 天皇誕生日 | 2月23日 | 天皇陛下の誕生日を祝い、国の繁栄を願う日 |
| 春分の日 | 3月20日 | 自然をたたえ、生きとし生けるものをいつくしむ日 |
| 昭和の日 | 4月29日 | 昭和の時代をふり返り、復興や平和への歩みに思いを寄せる日 |
| 憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の発展と平和を願う日 |
| みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しみ、その恵みに感謝し、豊かな心を育む日 |
| こどもの日 | 5月5日 | 子どもの健やかな成長と幸福を願い、母への感謝も伝える日 |
| 海の日 | 7月20日 | 海の恵みに感謝し、海とともに生きる日本の繁栄を願う日 |
| 山の日 | 8月11日 | 山に親しみ、その恵みに感謝する日 |
| 敬老の日 | 9月21日 | 長年社会に尽くしてきた高齢者を敬い、長寿を祝う日 |
| 秋分の日 | 9月23日 | 祖先を敬い、亡くなった人々をしのぶ日 |
| スポーツの日 | 10月12日 | スポーツを楽しみ、健やかな心と体を育て、活力ある社会を目指す日 |
| 文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を尊び、文化の発展を願う日 |
| 勤労感謝の日 | 11月23日 | 働くことの大切さを見つめ直し、互いの勤労を感謝し合う日 |
各祝日のより詳細な説明は、内閣府の下記ページをご覧ください。
各「国民の祝日」について - 内閣府
「祝祭日」という言葉で「祝日」「祭日」が混同されやすい
「祝日」と「祭日」が混同される大きな理由の一つに、「祝祭日(しゅくさいじつ)」という言葉の存在があります。
この言葉は、もともと戦前に「祝日」と「祭日」をまとめて指すために使われていた表現で、法律や新聞などでも広く用いられていました。
そのため「祝祭日=休みの日」というイメージが今も残っており、「祝日」と「祭日」が同一のものと誤解される要因になっています。
ただし、祝祭日は現在の法律上の正式な用語ではありません。
日常生活では今も目にすることがありますが、正確には「祝日」と「祭日」は別々の概念として扱われます。
まとめ
祝日と祭日の違いは、「法律で定められた日かどうか」です。
現行法に基づく休日は「祝日」であり、年間16日が国民の祝日として設定されています。
一方、祭日はかつて皇室や宗教的儀礼に基づいて定められた日で、現在の法律上には存在しません。
ただし、「紀元節」や「明治節」など祭日の一部は祝日に引き継がれています。
祝日と祭日の違いを押さえておけば、休みの日をより有意義に過ごせるでしょう。